Makoto
農学博士。1998年武田薬品工業入社。薬剤安全性研究所にて新薬開発の初期から後期までの前臨床安全性評価、特殊毒性評価、毒性機序解明、安全性バイオマーカー探索など幅広く従事。2010年、自然発生性網膜機能異常マウスにおける異常原因同定に関する研究で学位取得

FRONTEOなら創薬で社会貢献ができる。
そう信じて、日々取り組んでいます
いつまでも第一線で「ワクワク」していたかった
武田薬品工業での24年間を経て、FRONTEOに転職されました。「50歳までの転職」を考えていたそうですね

武田薬品工業で創薬プロセスを一通り体験したのですが、社内でのポジションが上がるにつれて現場から離れていかざるを得ない現実がありました。そんな時にふと「このままでいいのか」と思ったんです。本当に研究が好きで、年齢に関係なく第一線で「ワクワク」しながら挑戦を続けたかったんです。
50歳までに転職を目標に転職活動をしているなかで、エージェントからFRONTEOを紹介されました。AIの専門性はなかったのですが面接に行ったところ、なんと武田薬品工業時代の同僚だった豊柴博義(CSO)さんがやってきた(笑)。研究の話をよくしていた仲で、留学に際しては相談もしていたので、嬉しい驚きでした。久しぶりの再会でしたが、当然ながら話は盛り上がり、自然言語処理の可能性、特にNun Study(修道女を対象とした、言語能力と認知症の関係性の研究)の話を聞いた時には本当にワクワクしました。
そして何より、FRONTEOの「全ての人に等しく医療を提供する」というミッションに強く共感しました。今、薬が高額になりすぎて、誰もが等しく医療を受けられない未来が現実味を帯びてきています。自分の家族や友人が、薬が高額なために助からないなんて、絶対に嫌じゃないですか。もしAIで創薬を加速して価格が下げられるなら、それは本当に意味のあることだと思いました。
現在のライフサイエンスAI事業本部は、どんな組織なのでしょうか
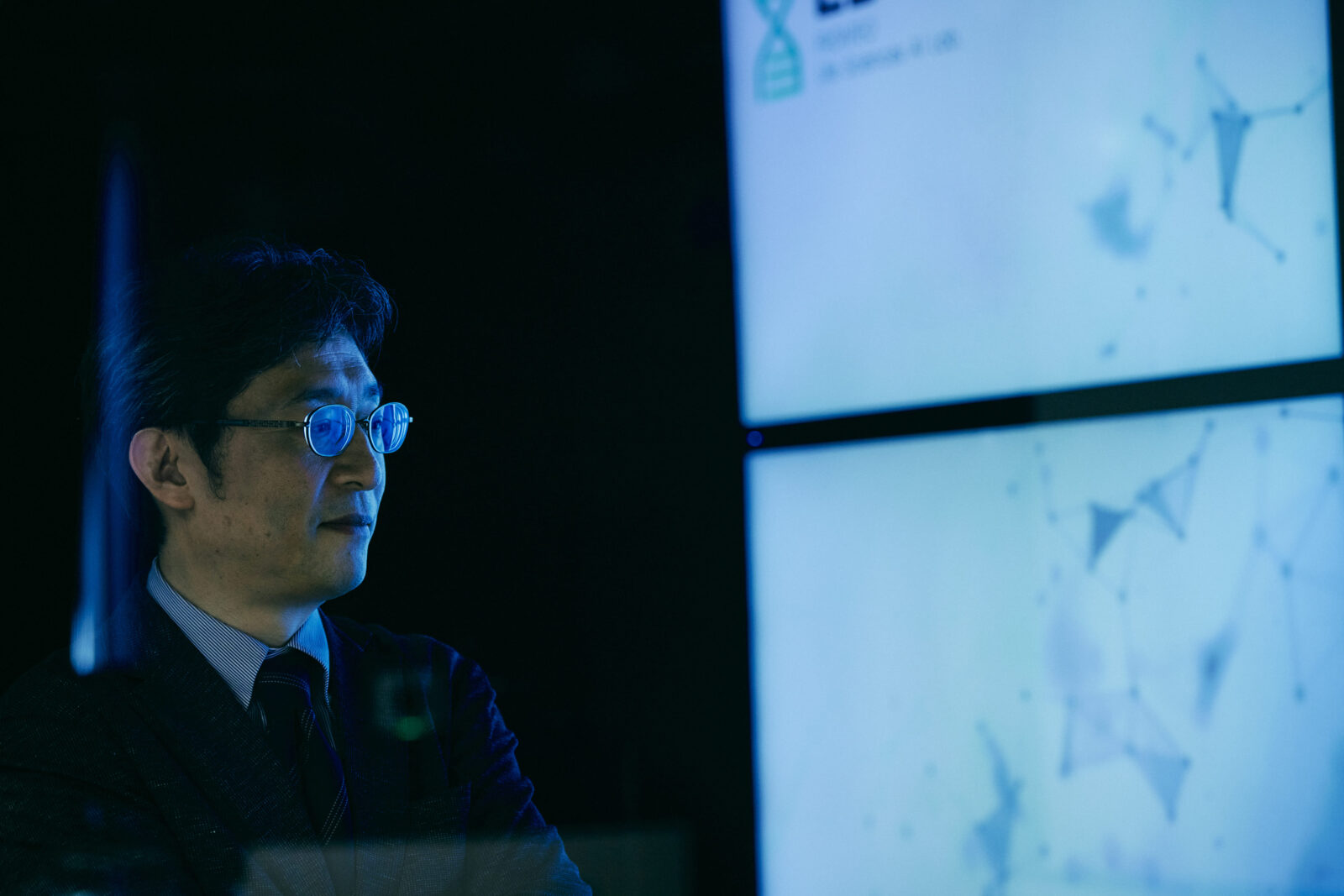
私たちのチームは18名で動いていて、10名がバイオロジスト、7名がデータサイエンティスト、1名がメディシナルケミスト(創薬化学者)という構成です。
一般的な製薬会社ではデータサイエンティストはデータサイエンティスト、バイオロジストはバイオロジストで仕事をしています。ですが、ライフサイエンスAI事業本部の最大の特徴は、バイオロジストとデータサイエンティスト、創薬化学者という異なる専門家が隣り合わせで仕事をしているところです。
この協働体制の最大の利点は、たとえばバイオロジストが大量のデータの紐づけに困っている場合、隣のデータサイエンティストが「エクセルよりもPythonの方が簡単にできますよ」と、最適な方法を教えてくれるんです。逆に、データサイエンティストが大量のデータをダウンロードして解析しても、疾患名や発症のメカニズムは分かりません。そんなときにバイオロジストが「この疾病はこういう特徴があります」という具合に補完することができる。
この相互補完をしている間にどんどん新しいアイデアが生まれてくるのが、他にはない強みなんです。データサイエンティストだけでもダメ、バイオロジストや創薬化学者だけでもダメ。皆が協働してはじめて、良質な仕事につながっていくんです。
KIBITは答えではなく、「大きなヒント」をくれる存在
現場で使われているKIBITですが、どのように活用されていますか?

私たちは今、KIBITによる解析とチームの知見を組み合わせた「Drug Discovery AI Factory」(DDAIF)というAI創薬支援サービスを展開しています。
私は、KIBITは答えを出すのではなく、大きなヒントをくれる存在だと思っています。それも人間では絶対に思いつかないような、飛躍したヒントをくれるんです。豊柴さんは「非連続的な発見」という言葉で表現していますが、私はこの特徴を「意図的なセレンディピティ」や「思考の飛躍」とも呼んでいます。
たとえば、ある結果を見て、ある人は「これは使えない」と言う。でも「もしかすると、化けるかもしれない」と勘づく人もいます。その違いは、その人が持っている引き出しの数と、新しい事象を柔軟に受け取れるかどうかによるところが大きい。

たとえば、ペニシリンを発見したフレミングも、たまたま培養シャーレに混入したアオカビの周りの細菌が増えていないことに気づいたから大発見に至ったと言われています。このような「偶然なる幸運」を、自然に任せるとしたら、我々はどれだけ待てばいいのか…。でもKIBITなら意図的に発生させることが可能なんです。
豊柴さんは数学者なのでどちらかというとシンプルさを求めますが、私はバイオロジストですのでイレギュラーな出来事やカオスなモノほど、心が躍ります。生物は種を絶やさないために、バラエティを持たせるようにできていて、研究の第一線にいたいのも「こんなモノがいるの?」と驚きたいからでもあります。FRONTEOには、数学と生物学の融合があり、それが非連続的発見から創薬へとつなげる土壌を育む要素になっているのではないか、と思っています。
現在、力を入れていることはなんですか?

クライアントのニーズである新規標的探索やドラッグリポジショニング(既存の薬を転用する)に全力で取り組んでいます。そしてKIBIT発の新規な標的や適応症が、一日も早く臨床でその有効性が確認されることを心より願っています。
一方で、我々自身もできることを少しずつでも実施していきたいと思っています。ひとつは希少疾患への取り組みです。患者数が少なく、症例が集まらないためメカニズムも明らかになっていない希少疾患はたくさんあります。多くの製薬企業も希少疾患にフォーカスしているとはいえ、あまりに患者数が少ないと製薬企業は手を出せません。なにしろ一つの薬の開発費は数百億円以上とされていますから。
ですがKIBITを使えば、少ないデータでも解析できますし、効果が得られる既存薬の発見も可能だと思っています。ドラッグリポジショニングであれば、かなり開発コストが抑えられます。根本治療は難しくても、対処療法で患者さんの体調が少しでも良くなれば、それは大きな意味があると思います。
もうひとつは個人的な思いでもありますが、熱帯病が気になっています。マラリアはよく知られる熱帯病ですが、ほかにも多くの顧みられない熱帯病が存在しています。そういう疾病に対する治療薬の発見にKIBITで迫れると面白いですよね。「世界中に薬を待っている方がいる」という思いが、私たちの原動力になっています。
FRONTEOなら創薬で社会貢献ができる
どんな人がFRONTEOに向いていると思いますか?

一番大事なのは柔軟性ですね。既成概念にとらわれず、KIBITからのヒントを素直に受け取れること。「これは、面白いかもしれない」と思えるセンスやひらめきが絶対に必要です。また、ぱっと見たところダメでも、別の角度から見るとOKだったりしますから、粘り強く取り組める方が向いています。
あとはやはりコミュニケーション能力は欲しいですね。バイオロジーとデータサイエンスという異分野の人たちが協働している現場ですから、互いの交流はもちろん、お客様である製薬会社との信頼関係も大切です。
うちのチームにはお金やキャリアを求めるのではなく、「死ぬまでに一薬創りたい」と口にするメンバーが何人もいます。それほど薬を創るのは難しいことなのですが、それでもDDAIFをビジネスにしているFRONTEOなら可能性は高い。創薬で社会貢献できる、そう信じて日々、取り組んでいます。
そして何よりFRONTEOに合うのはワクワクしたい方でしょうね。メンバーの皆さんを見ていると、とにかく楽しそうなんですよね。私は50代ですが、転職以来、ずっとワクワクし通しです。年齢に関係なく、いつまでも第一線で挑戦し続けたい。そういう気持ちを持っている人と共に、すべての人に等しく医療を届ける未来を目指したいですね。

Text:Yoko Koizumi/Photo:Shintaro Yoshimatsu
